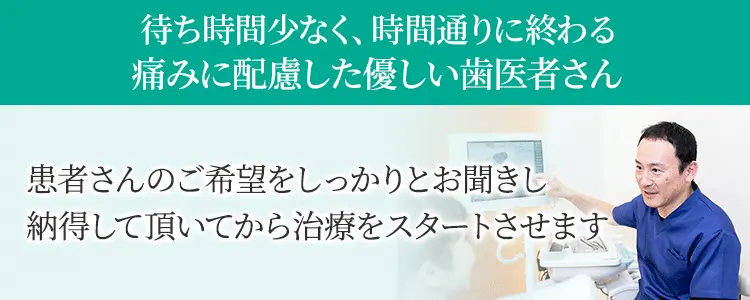こんにちは。サカモト歯科です。
みなさんは自分の歯の咬み合わせを意識したことはありますか?食事を問題なくできている場合でも、実は不正咬合と呼ばれる咬み合わせが悪い状態にあたることもあります。不正咬合を放っておくと、歯の健康だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼします。
この記事では「咬み合わせが悪いとはどんな状態なのか」「不正咬合の種類とは?」について詳しく解説していきます。
正しい咬み合わせとは?
咬み合わせの正しい状態とは、上下左右が対称であり、上下前後に2〜3ミリ程度重なっている状態です。一方咬み合わせが悪いと、上下の歯がうまく咬み合わず、食べ物を噛み砕く効率も悪くなってしまいます。咬み合わせが悪い状態は一般的に不正咬合と呼ばれ、それぞれ特徴があります。
不正咬合の種類
叢生(そうせい)
歯が重なり合っていたり、凸凹になっている状態です。八重歯も叢生に含まれます。叢生になってしまう原因は、顎の大きさと歯の大きさのバランスがとれていないことだとされています。そのほか、指しゃぶりや舌の癖などによって生じることもあります。
上顎前突(じょうがくぜんとつ)/出っ歯
下顎の歯よりも、上顎の歯が前方に出ている状態です。顎の位置によっては突出して見えることもあり、見た目も大きな影響を及ぼすことも少なくありません。遺伝的要因もあれば、癖などの生活習慣が原因になることもあります。
下顎前突(かがくぜんとつ)/反対咬合・受け口
下顎全体または、下の前歯が上顎よりも前に出ている状態をさします。下の歯を舌で押す癖があったり、顎の成長不足によって生じると言われています。
空隙歯列(くうげきしれつ)/すきっ歯
歯と歯の間に隙間がある状態で、見てわかるほど隙間が広いケースもあります。
隙間は部分的に生じることもあれば、全体的に生じることもあります。原因はさまざまですが、生まれつき歯の本数が少ないことが原因となり生じることもあります。
開咬(かいこう)
奥歯を咬み合わせても、前歯が咬み合わず隙間が生じる状態です。口呼吸や舌癖、指しゃぶりなどの習慣が原因で生じることもあります。
過蓋咬合(かがいこうごう)
上下の歯を咬み合わせた際に、上の歯が下の歯に覆いかぶさりほとんど見えない状態をさします。上顎よりも下顎の位置が後方にあることによって生じます。
交叉咬合(こうさごうこう)
部分的に咬み合わせが逆になっている歯列の状態です。口呼吸や頬杖が原因で起こるケースもあります。
切端咬合(せったんこうごう)
咬み合わせた際に、上と下の前歯の先端がぶつかり合う状態です。顎骨の成長が原因となるケースや、口呼吸や舌癖が影響して生じることもあります。
不正咬合を放っておくとどうなる?
ケアしにくく虫歯や歯周病になりやすくなる
不正咬合の種類によってはケアしにくく、汚れが除去しきれないため、虫歯や歯周病のリスクも高くなります。
顔に歪みが出やすくなり、コンプレックスを抱えやすい
不正咬合は表情筋や咀嚼筋(そしゃくきん)のバランスに影響を与え、顔を歪ませることもあります。また、口元のバランスが悪いとコンプレックスを抱えやすくなります。
頭痛・肩こりといった全身の不調が起こりやすい
咬み合わせが悪いと、あらゆる筋肉のバランスを崩すため、首や肩のコリをはじめ、頭痛などの全身の慢性的な不調が見られることもあります。
当院の咬み合わせ改善治療
不正咬合に当てはまる場合は、早めに改善することが望ましいです。癖や悪い習慣を改善することも大切ですが、生活習慣の改善だけではよくならないケースもあります。不正咬合を治すには歯列矯正治療がおすすめです。ワイヤー矯正だけでなく、最近は見た目も目立たず痛みも伴わないマウスピース矯正も人気があります。また、当院では小さいうちから正しい歯並びを誘導できる小児矯正も行っております。大人の方はもちろん、お子様の歯列でお悩みがある場合もぜひご相談ください。
当院の咬み合わせ改善治療に関する詳細はこちら▼
https://sakamoto-dent.net/kami/
まとめ
矯正治療をすると、歯列が整い咬み合わせも改善されます。すると、見た目も美しくなり日頃のケアもしやすくなります。生活に特に問題がないからと放っておいてしまうと、後々大きなトラブルになりかねません。不正咬合でお悩みの方は、歯列矯正治療を検討してみてください。